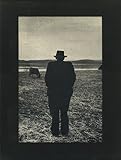これまで話してきた内容は、
アーネストの弟子である森村泰昌氏の、
解説によるところがほとんであります。
多少、私の話も書きましたけれど、
基本的には直弟子である森村氏による、
お話しです。
さて、他の人はどう思っていたのでしょう?
いわゆる「写真家」の中で、
アーネストは知られていたのでしょうか?
この一連の記事の元ネタである、
1999年6月号の芸術新潮。
これによりますと、実はアーネストは、
「知っている人だけ知っている人」
つまり、業界でも著名ではなかった、
ことが分かるんですね。
写真家の畠山直哉氏が書いている、
アーネストの写真との遭遇や、
その著書の内容、モダニズムという世界、
それらを少しまとめてみたいと思います。
まず、畠山直哉氏の説明から。
有名なのは、こんな作品群ですね。




この写真集が、特に評価されています。
その畠山氏も、実は知らなかったと、
書いていたのです。
名前は知っていたけれど、
のレベルだったようです。
その畠山氏が、アーネストの書いた本、
「35mm Nega and Prints」
という、アメリカで出版された技術書から、
引用している言葉が、実にモダニズム的で、
奇妙に切ないのです。
我々は技術をマスターしなければならない。だが技術は、それ自身では全く意味のないものなのだ。
我々は人生の意義を表明し、自然の美を捉え、世界の実態に踏み込んでいくための。その方法を発見しなければならないのだ。(p14)
この若きアーネストの文章を読んで、
畠山氏が書いた文章を読んで、
私が思うのは、それが可能だ
と信じた時代があった。
それがモダニズムといえるのではないかと。
畠山氏が好きなアーネストの作品を上げているんですが、
それがこれらです。


畠山氏はこう書いています。
そういった写真が、「フィルム」や「露出」を説明するために使われていたりする。なんだか贅沢だ。
その後、畠山氏は1960年代に、
アーネストが日本で
どのような評価を受けていたかを、
調べるのですが。。
畠山氏によると、
見つかった文献はこれだけだそうです。
「アーネスト・サトウ写真展」は、一種のサロンピクチュア的なあまさがつきまとっていて、印画仕上げの美しさだけが印象に残る写真展だった。
アサヒカメラ1964年9月号
当時の日本で写真の主流だったのは、
リアリズム。
端的に言えば、汚い世界を好む考え方です。
しかし、だれもこれらを見て、


これしか書かなかったんでしょうか。
評者には木村伊兵衛もいたと言うのに。
いかに彼が、日本で受け入れられなかったかを、
示しているように思われます。
アーネストの考える「モダニズム」。
その一方で、複雑なものに支配されている、
一種のアニミズム的現実。
今も変わらない、それを思う度に、
私自身が複雑な思いにとらわれるのです。

畠山氏が最後に書いている文章は、
そのやるせなさを、よく表していると思います。
ディオゲネスは街路で、ランプをかざして「人間」を探して歩き回ったという。そんなことをしても「人間」がその辺の隠れているのを見つけ出せるわけではない。「人間」はそれを探して歩き回る行為のまわりに、観念として浮遊しているだけだ。だがそれでも、「人間」を探すことなしには僕たちは生きてゆけない。僕たちはいつも「人間」を待ち続けている。
カメラを構える写真家は、ランプをかざす哲人にほかならない。アーネスト・サトウもそう信じていたはずだ。
新進気鋭時代の畠山氏が、
言葉を選んで書いたであろう、
この文章。
勇気が必要だったはずです。
私は敬意を払いたいと思います。
(もちろんつづきますよ!さあ、小難しいこと抜きで、クリックでもどうです?)

- 作者: Y.アーネストサトウ,高階秀爾,Y.Ernest Satow
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1998/10
- メディア: 大型本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (2件) を見る
![芸術新潮 1999年 06月号 [特集 カメラ好き集まれ!] 芸術新潮 1999年 06月号 [特集 カメラ好き集まれ!]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61NDRrSzTSL._SL160_.jpg)